第64回「奥の細道」羽黒山全国俳句大会開催
10月29日(土)、30日(日)の両日、第64回「奥の細道」羽黒山全国俳句大会が開催されました。
羽黒吟社としては、羽黒地域内の小学校での俳句指導、兼題投句の校正、本大会の会場準備、披講などで協力させて頂きました。
29日(土)は、選者の伊藤伊那男先生(「銀漢」)をお招きして、子供の部の選評と表彰が行われました。
全国の小中学校から寄せられた1681句から、選者の伊藤先生と今回は参加が叶わなかった対馬康子先生(「麦」・「天為」)が選ばれた入選句につき、伊藤先生が選評してくださいました。
羽黒吟社で俳句指導にうかがった羽黒小や広瀬小の児童の作品も入選句に入っていて、大変嬉しく感じております。
30日(日)は、受付後「鳥渡る」「芋煮会」の席題での投句の後、伊藤伊那男先生に「奥の細道/芭蕉の謎・曽良の謎」の演題でご講演を頂きました。
様々な資料の積み重ねから芭蕉や曽良の出自を推定するお話は、これまでの芭蕉・曽良研究にはあまりみられなかった話ながら、説得力があり、興味深かったです。
午後からは兼題の部、席題の部の選評・表彰が行われ、羽黒吟社からも以下の方々が受賞されました。
[対馬康子先生選]
兼題の部
[特選]
金野市子 月山に一日辞儀して稲穂かな
[伊藤伊那男先生選]
席題の部
[特選]
長南美恵 芋煮会泡を滾す落し蓋
今井辰美 分校のリヤカーも出て芋煮会
[佳作]
陶山芳子 色鳥来夫の育む屋敷林
今井辰美 小鳥にも早口言葉あるらしき
吉住弘幸 鳥渡るなにもせぬまま日も暮れて
〃 鳥渡る安らぎゐたり今日ひと日
安藤幸子 小鳥来る色よき実より啄めり
今年もコロナ禍のため、前夜句会は行われなかったものの、兼題の部には前回を上回る投句を頂きました。
歴史と伝統ある「奥の細道」羽黒山全国俳句大会を今後さらに盛り上げていくよう、羽黒吟社としても陰ながら協力していきたいと思います。
大会運営に尽力された関係者の皆様、ご苦労様でした。

























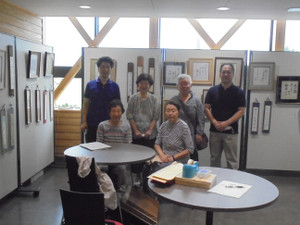
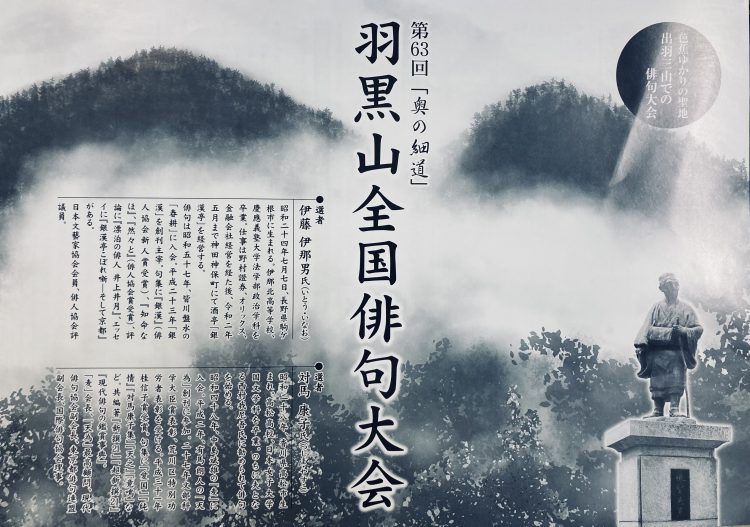
最近のコメント